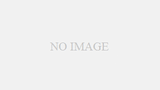今朝の集英社オンラインの記事で、興味深いものがあった。「テレビのリアルタイム視聴が2012年から2023年に16.4%も減少している」という内容である。
ここでいう「テレビのリアルタイム視聴」とは、テレビを録画等しないで、リアルタイムで見た人の割合を示しているのだが、中身をよく見ると、テレビをつけて少しでも地上波や衛星放送が映っていたり、病院の待合室などで受動的にテレビを見た場合もリアルタイム視聴として集計しているのだという。能動的にテレビ番組をリアルタイムで見た人の割合ではないので、注意してほしい。
それでも統計として毎年集計しているので、10年以上のデータが存在しているのだが、それによると、2012年には87.5%もリアルタイム視聴をしていたものの、2023年には71.1%まで下がっているという結果になっている。それがタイトルにも記した、「テレビのリアルタイム視聴が10年間で16%も減少」につながっている。
では、テレビのリアルタイム視聴が減った分はどこに行ったのかというと、インターネットである。2012年には71.0%の「インターネットの行為者率」は、2023年に91.2%まで上がっている。
ただし、この数字を持ってテレビ離れになっているのかは疑問の余地がある。NHKプラスやTVerといったテレビの見逃し配信もこの中に含まれるからである。さらに、テレビ局がYouTubeで番組を配信している例もあるので、一概には言えない。
とはいえ、地上波、衛星放送の受信機でリアルタイムでテレビを見る人は減っているのは確かである。
僕の場合も、夕方、食事をしながらニュースを30分ぐらいはリアルタイム視聴していることは多いが、それ以外であまりリアルタイム視聴はしていない。元々ホームシアターを構築する際に大画面テレビがないと、映画などが見られないので、テレビを買っているので、あまり地上波や衛星放送には関心を持っていない。ニュースも見るが、毎日大谷翔平の話題ばかり取り上げているので、「違う問題はいくつもあるだろう」と不満は募っている。その不満はYouTubeの配信である程度晴らしている。
今の若い人はテレビを持たないことも多いと聞く。僕が福岡にいた時の隣の部屋にいた学生さんは、引っ越す時に荷物がとても少なく、テレビを運び出すという行為をしていなかったように思うので、意外に感じたものだが、動画をPCやスマートフォンで見るという習慣になってしまっているのならば、テレビが不要なのも納得がいく。
僕は映画はPCやスマートフォンでは見たくないので、大画面テレビ一択である。チューナーはあってもなくてもいいが、画面サイズにはある程度こだわる。地上波にも衛星放送にも期待はしていないが、ニュースソースとしてはもう少し奮起してほしいと思えなくもない。SNSがニュースソースだと情報源が不確かだからである。