僕がこの本の刊行を知ったのは、沖縄と東京の二拠点生活を続け、沖縄に関する書籍も多数出している藤井誠二さんの新しいノンフィクション書籍として、「ソウル・サーチン」が出ると聞いたからである。しかし、それだけが購入し、読む理由になっているのではない。共作者として新里堅進さんの名があったからというのもある。
新里堅進さんの名だけはSNSのXで、沖縄在住の方々からの書き込みで知っていた。知っている人は知っている漫画家だということだけは知っていた。その新里堅進さんの漫画が読めるというのも読むきっかけの一つではある。
8月4日には家に本が届いたが、読み終わるまでに1ヶ月半近く要してしまった。原因はその本のサイズと分量である。まるで百科事典のような大きさと900ページにも及ぶ分量は、普段本を読む際の姿勢であるベッドに寝っ転がるということができない。きちんと椅子に座って膝に本を置き読まないと読み進められないので、毎日読むことはできず、週に1回、30分ぐらいずつ読めればいい方であった。そのため、予想外に時間を要してしまったのだが、内容は面白く、つまらないから先に進めないというわけでは全くない。今日読み終わったのは、体調的にホームシアターで映画を観る気がわかなかったので、代わりに「ソウル・サーチン」の途中から読み進めていったら、内容は面白いので途中で止まらなくなって、最後まで読み進めてしまったからである。
本の構成は、藤井誠二さんによる新里堅進さんの評伝部分と、新里堅進さんが生み出した数々の漫画の中から代表的な作品を再収録するという二重構造で作られている。もちろん評伝部分と漫画の部分の両方を読めば、作品の意図などが見えてくるのであるが、単純に評伝部分だけ読んでも面白いし、漫画だけ読んでも面白いと思う。
藤井誠二さんによる新里堅進さんの評伝は、藤井誠二さんの他の本と同じく新里堅進さんの人生や性格を、彼と関わりのあった人たちに聞き込み、それを本人に確認するという形式で進んでいくため、新里堅進さんという人物が見事に立ち上がってくる。Xでは何人かの沖縄在住の方が名前をあげていたものの、知る人ぞ知る漫画家だったのは、新里堅進さんが売れることを考えてもおらず、他の人たちとの交流をも好まず、ただ一心に沖縄戦や沖縄の歴史だけを描き続けたいがために自分の知名度を上げる努力を全くしていないことに起因する。新里堅進さん自身、書いた漫画の原稿をほとんど管理していないために、「ソウル・サーチン」制作における漫画の再録に大変な苦労がかかったと記されている。
その新里堅進さんの漫画が多数再録されているのがこの本の特徴で、特に沖縄戦にまつわる漫画の描写の数々は、もし僕が子供の頃に読んでいたのならば、その客観性に圧倒されると同時にトラウマになってしまったのではないかと思われる緻密な描写である。現在、歴史修正主義者たちがあまりにおかしなことを発言し、それをお詫びすることなく開き直る事例が多数見られるが、新里堅進さんの漫画を読むと、それを否定するかのような沖縄戦の実態が漫画という媒体を通して見えてくる。新里堅進さんの漫画をこの「ソウル・サーチン」以外で読むことは現在不可能に近いので、かなり貴重な本になっている。
最後に編者である安東崇史さんの解説も入っているが、この解説自体も作品を補強する内容になっていて、興味深い。沖縄戦における日本軍の加害性が語られ始めたのは意外と新しい時期になってからという解説は少々驚いたが、考えたら僕がショックを受けたひめゆり学徒隊が自分の体験を語る場となった、ひめゆり平和祈念資料館の開館が1989年と僕が初めて沖縄を訪れた1992年の3年前という事実からしても、古い話ではないのかもしれない。沖縄をめぐる問題だけでなく、日本の戦争責任について、あまりにも偏った意見を持つ人が多くなってきた中、それを考え直す契機としてこの本が持つ意義は大きいのかもしれない。
本としての分量は多いし、価格も3850円と気軽に買える本ではないのは十分承知だが、あまりにおかしい方向に進みつつある日本と沖縄において、改めて太平洋戦争とはなんだったのか、沖縄戦とはなんだったのか、平和とはなんなのかを考えるためのテキストとして、この「ソウル・サーチン」の持つ役割は大きいと考える。

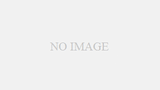
コメント